


OMOIDE ESTATE
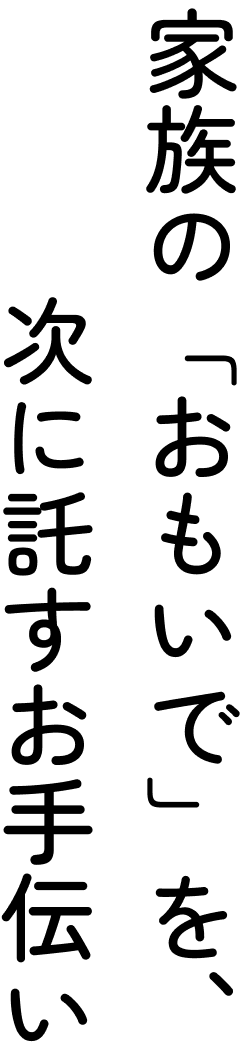
WHAT'S NEW
REASON

01

02
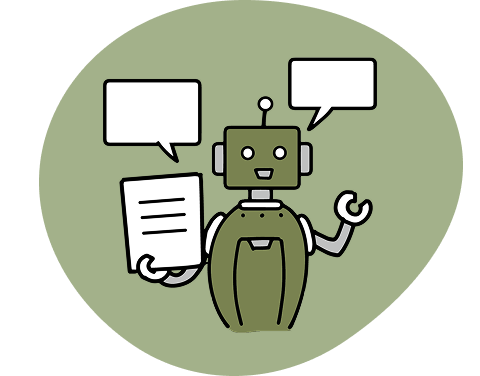
03
FEEDBACK
勉強会ありがとうございました!
こういう機会があるおかげで、一人で悩まず考えなくて済むので本当にありがたいです!!
今回、売る予定の土地は、周囲に似たような環境物件で売りに出た例がありません。
さらに雑木林で埋め尽くされているため、土地の全貌も見えず、不動産屋さんもかなり大変なのだろうとは思います。
セミナーのおかげで地道に、売却に向けて頑張っていけそうです。
住民票も移動してからも3年以内なら3,000万円の控除があることは知りませんでした。不動産屋さんならではの情報をありがとうございました。
今回はいろいろ初めての事で、話を聞いているだけで精一杯で、売却時は専任がいいのか、一般的いいのかなど、その辺りの情報がわからなかったのでまた勉強させていただきます。
また説明会に参加して、質門や検討させていただきたいと思います!
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
本日はお忙しい中、色々とわかりやすく説明して下さってありがとうございました。
囲い込みについては、ある程度は認識していましたが、専任でも2パターンあることは知りませんでした。
家の売却にあたり、借地と賃主へのアプローチの対応について、 色々と悩んでいました。
あらかじめ買取の相場感を先に調査した上で、相手の方の希望を聞いていくことがとても参考になりました。
実際に取り組んでみようと思います。
USEFUL COLUMN